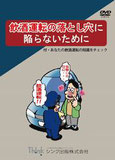私は普通自動車第一種運転免許しか持っていませんが、2024年の4月から、一部の地域でライドシェアが解禁されたと聞きました。ライドシェアはタクシー不足を補完する仕組みのようですが、普通免許でも営業できるとSNSで見たのですが本当でしょうか?
■新たに導入されたライドシェアとは

ライドシェアとは、一般のドライバーが、自家用車を使用して乗客を有償で運ぶサービスです。
海外でライドシェアを採用しているところでは、大きく分けてUberなどのプラットフォーム事業者による管理を義務付けているTNC型と呼ばれる形や、運転手に対して登録や車両・運行管理を義務付けるPHV型と呼ばれる形での運用が行われていますが、特に規制のない国もあります。
一般の運転手が、好きなときに自宅などから行くことができるため、時間的・場所的な需要に応じることができ、またタクシーより安価な場合も多いので、拡大傾向にあるようですが、安全面や事故が生じた際の賠償責任を負えるかなどの疑問もあり、導入していない国もあります。
■日本型ライドシェア導入の経緯

日本では、2024年4月から、いわゆる日本型ライドシェアと言われる制度が開始しています。
日本では元々、自家用自動車を使用した旅客の運送を有償で行うことは、いわゆる白タク行為として違法とされていました。
道路運送法78条により、自家用自動車は原則として有償で運送の用に供してはならず、災害のため急を要する時を除き、例外的にこれを行うためには、国土交通大臣の許可又は登録を受けるべきことが定められています。
また安全面の懸念や既存業者の利益を害するなどもあって、ライドシェアの導入にはタクシー業界などからも否定的な意見も出ていました。
しかし近年、観光地や過疎地等におけるタクシー不足が顕著な問題になっており、検討が進められた結果、要件を緩和して日本型ライドシェアといわれる自家用車活用事業ができるようになりました。
すなわち、道路運送法78条本文は、自家用自動車は次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならないとされ、許される場合としては、以下の3つの場合となります。
- 災害のため緊急を要するとき(1号)
- 市町村やNPO法人等が地域住民や観光客等の運送を行うとき(2号・これを自家用有償旅客運送といいます)
- 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき(3号)
日本型ライドシェアといわれるのは同3号に基づくものになります。
■日本型ライドシェアの概要

日本型ライドシェアの実施区域は、当初、東京23区と武蔵野市、三鷹市、並びに横浜市など神奈川県内の一部地域、名古屋市など愛知県内の一部地域、京都市など京都府の一部地域で順次開始され、拡大しています。
タクシーの乗務員は普通自動車第二種免許が必要ですが、ライドシェアのドライバーは普通自動車第一種免許(いわゆる普通免許)を取得して1年以上の者であれば稼働することができ、また自家用の普通自動車を使用することができます。
ただし、日本型ライドシェアでは、個人で勝手に業務を行うことはできず、タクシー事業者への登録が必要です。
タクシー事業者にはタクシードライバーと同等の指導等を行う体制が確立されていることが必要とされ、実際には当該タクシー事業者における研修等の指導をうける必要があります。
その他タクシー事業者には、運行管理者の選任や点呼・指導監督・研修等の体制や設備、責任体制や緊急時の連絡、協力体制の確立等が運行管理規程に定めることなどが求められており、ドライバーの教育や運行管理、整備管理を行うものとされています。
また、このような制度であるため、タクシー事業者は使用者責任、及び運行供用者責任を負うものと解され、事故が生じた場合の責任は、タクシー事業者も同責任を負うことになります。
なお、本制度はタクシー不足の解消を主眼としており、「地域又は期間を限定して運送の用に供する」ものですので、国土交通省により、区域毎にタクシーが不足する時間帯のみ運行が認められています。
また、日本型ライドシェアでは乗客の支払う運賃はタクシーと同様とされています。
■まとめ
以上のように、日本型ライドシェアはあくまでもタクシー不足を補完するという扱いであり、いわゆる普通免許を持っていれば個人が一人だけで始められるというものではありません。
ただ、上記の各条件を満たせば、自分の好きな時間に稼働することもできるものであり、副業や職業選択の幅が広がるものと考えられます。
道路運送法等の規制が厳しい日本でライドシェアが今後どうなっていくかは明らかではありませんが、需要や供給の状況などに応じて範囲や内容も変化していくものと思われます。

執筆 清水伸賢弁護士
WEB連載中の「安全管理の法律相談」を厳選してまとめた小冊子を発売中!
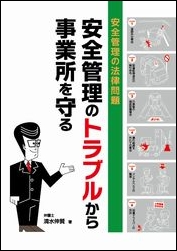
No.1078 安全管理のトラブルから事業所を守る(A4・16p)
本誌は、事業所の安全管理業務を行うに当たり、様々な法律上のトラブルから身を守るために知っておきたい法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説する小冊子「安全管理の法律問題」の続編です。
経営者や管理者が正しく法律知識を身につけ、対策することで、事業所全体の安全意識の向上へとつながり、交通事故を始めとした様々な法律上のトラブルが発生するリスクも低減することが可能となります。
(2021.12月発刊)

No.1053 安全管理の法律問題(A4・16p)
本冊子は、事故・トラブルとして6つのテーマを取り上げ、使用者責任や運行供用者責任といった事業所にかかる責任の解説をはじめとして、経営者や管理者として知っておかなければならない法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説しています。
法律知識を正しく理解することで、事業所の問題点を把握することができ、交通事故のリスクを低減することができます。
(2017.12月発刊)
 シンク出版
シンク出版