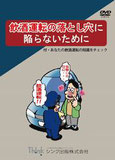2025年4月1日より変更された二輪車の免許区分について質問なのですが、弊社の従業員の多くは原動機付自転車で通勤をしています。各々、原動機付自転車の免許か普通自動車第一種免許で原付を運転しているのですが、今回の免許区分の変更で何か影響があるのかを教えてください。
■二輪車の免許区分の変更と2024年11月の改正

2025年4月以前においては、原動機付自転車の総排気量は50cc以下とされ、最高出力の規制はなく原動機付自転車の免許か、普通自動車第一種免許があれば運転することができました。
そして総排気量が50ccを超え、125ccまでの二輪車には、小型限定普通二輪免許が必要とされてきました。
しかし国土交通省と警察庁は、2024年11月、道路交通法施行規則および道路運送車両法施行規則の一部を改正し、いわゆる原付免許で運転できる二輪車の範囲を広げました。同改正は2025年4月1日から施行されています。
まず道路交通法第2条第1項第10号イの規定は、原動機付自転車の定義のうちの一つを「内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用いる車」としていました。
同条項を受けて道路交通法施行規則第1条の2は、「内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあっては、総排気量については0.050リットル、定格出力については0.60キロワット」としており、これがいわゆる原付免許と普通免許で運転できる原動機付自転車としていたのです。
この条文が今回改正され、「内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあっては、総排気量については0.050リットル(二輪のもののうち、構造上出すことができる最高出力が4.0キロワット以下の原動機を有するものにあっては、0.125リットル)、定格出力については0.60キロワット」とされました。
すなわち、二輪の原動機付自転車のうち、総排気量が50cc以下のものだけではなく、最高出力が4kw以下であれば、総排気量が125ccまでのものまでがいわゆる原付免許や普通免許で運転できることとされたのです。
これに伴い、道路運送車両法施行規則も改正され、新たなものについては型式認定において総排気量に加え最高出力も表示させることとされています。
■改正の経緯

今回の改正には、大きく分けると二つの理由が考えられます。
一つ目は、そもそも排気量50cc以下の新型原付については、メーカーの開発や販売数が減少しているということが言われています。
近年の電動アシスト自転車その他の移動手段の普及や、違法駐車の取締り強化などにより、販売数が減少して採算が取りにくくなっているというのです。
そして二つ目として、二輪車の排出ガス規制が大きな原因と言われています。
2019年2月に施行された道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正により、ガソリン直噴車や二輪車等の排出ガス規制の基準が強化されていますが、継続生産している第一種原動機付自転車についても、2025年11月から適用が開始されることになっています。
排気量50ccの原付では、同排出ガス規制の基準を満たすことは、技術面でも困難であるといわれており、規制をクリアする原付の生産や販売が困難となる見込みであり、そのような事情も今回の改正の背景にあるといわれています。
ちなみにこの排出ガス規制は、新規に生産されるものが対象ですので、既に購入している原付が使用できなくなるわけではありません。そのため、ただちに買い換え等をしなければならないというものではありません。
■免許区分変更の影響

今回の改正の経緯等は以上のようなものであり、施行前において50ccのいわゆる原付に乗っていた人について突然何かが変更するというものではありません。
今までの原付の範囲が広がるというだけであり、当然原付免許ないし普通自動車免許で乗れますし、法定速度は時速30kmです。
ヘルメットの着用義務、大きな交差点での二段階右折が必要であること、原則は第一通行帯を通行すべきこと、二人乗りの禁止、高速道路等の通行禁止など、従前の原動機付自転車が守らなければならない交通法規はそのまま適用されます。
なお、小型限定普通二輪免許で乗れるバイクは、最高出力4kw以下という規制はなく、最高速度も時速60kmであり、二人乗りも可能で、二段階右折の必要もありません。
そのため、同じく総排気量125cc以下となったからといって、今回施行される新基準の原付免許が、小型限定普通二輪免許と同じになるわけではなく、守るべき交通法規等が変わるわけではありませんので、注意が必要です。

執筆 清水伸賢弁護士
■WEB連載中の「安全管理の法律相談」を厳選してまとめた小冊子を発売中!
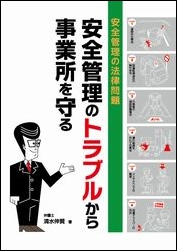
No.1078 安全管理のトラブルから事業所を守る(A4・16p)
本誌は、事業所の安全管理業務を行うに当たり、様々な法律上のトラブルから身を守るために知っておきたい法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説する小冊子「安全管理の法律問題」の続編です。
経営者や管理者が正しく法律知識を身につけ、対策することで、事業所全体の安全意識の向上へとつながり、交通事故を始めとした様々な法律上のトラブルが発生するリスクも低減することが可能となります。
(2021.12月発刊)

No.1053 安全管理の法律問題(A4・16p)
本冊子は、事故・トラブルとして6つのテーマを取り上げ、使用者責任や運行供用者責任といった事業所にかかる責任の解説をはじめとして、経営者や管理者として知っておかなければならない法律知識を清水伸賢弁護士がわかりやすく解説しています。
法律知識を正しく理解することで、事業所の問題点を把握することができ、交通事故のリスクを低減することができます。
(2017.12月発刊)
 シンク出版
シンク出版